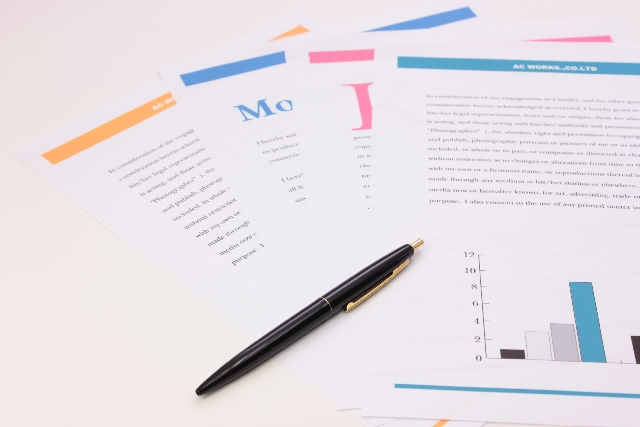


分かりにくい文章と思いますが、最後までお付き合い下さい。
厚生年金記録と失業保険(受給金額は、一切関係無いものとする)記録についてお聞きします。
例えば、今年7月一杯で自己都合で退職後、前職場の厚生年金記録更新?年金支払い?は途絶えるのは理解できますが、11月から失業保険を受給した記録は残りますか?
契約期間終了の場合でも、8月?から失業保険を受給した記録は残りますか?
また、履歴書の職歴欄に「7月一杯で一身上の都合により退職」のところを「今年4月からの4ヵ月契約期間終了により退職」と記入すれば、不採用や給料減額や解雇される原因になりますか?
非常に分かりにくいと思いますが、皆様の紳士的な回答をお願いします。
厚生年金記録と失業保険(受給金額は、一切関係無いものとする)記録についてお聞きします。
例えば、今年7月一杯で自己都合で退職後、前職場の厚生年金記録更新?年金支払い?は途絶えるのは理解できますが、11月から失業保険を受給した記録は残りますか?
契約期間終了の場合でも、8月?から失業保険を受給した記録は残りますか?
また、履歴書の職歴欄に「7月一杯で一身上の都合により退職」のところを「今年4月からの4ヵ月契約期間終了により退職」と記入すれば、不採用や給料減額や解雇される原因になりますか?
非常に分かりにくいと思いますが、皆様の紳士的な回答をお願いします。
厚生年金記録に失業保険の受給履歴や退職理由は載りません。厚生年金記録には、在職中の会社名と厚生年金加入期間と標準報酬月額と納めた保険料しか載りません。
履歴書には虚偽記載をしない限り減給や解雇事由にはなりません。但し、履歴書を書式通りに記入しないと採用前の書類審査で落とされる可能性は高いと思います。
履歴書には虚偽記載をしない限り減給や解雇事由にはなりません。但し、履歴書を書式通りに記入しないと採用前の書類審査で落とされる可能性は高いと思います。
失業保険の不正受給ですが、友人が働いていたいた会社に採用になった人は、前職をリストラになり会社都合の退職ということですぐに失業保険が支給されているのですが、その人と社長は元々知り合いらしく、
失業保険をもらっている間は社員とせず、アルバイトという形で使っているとのこと。その人と社長の間では、給料ではなくアルバイト代として手渡しで支払い、なおかつ領収書はその人の奥さんの名前で領収書を切っているということでした。
その場合明らかに不正受給ですが、証拠としては何も残っていないようですし、会社はその人とは関係ない、といってしまえばそれまででしょうか。 不正受給をしている人は丸々1年不正受給をしているようです。
私の友人はその会社で働いていましたが、売上数字が上がらないということで、給料を下げられた上、今後どうするのか、給料をさらに下げて、社員として働くか、それとも別の職を探すか、ということを問い詰められ、結局退職しました。
社員として働いていた人の給料を下げて、失業中の人を別人として扱って雇いアルバイト代を支払っている。
なんか腑に落ちなくてスッキリしません。 そのことは会社内でしかわからないことらしく、会社以外の人は誰も知らないということなので、もし私が密告したらその辞めた友人が、辞めさせられたことを逆恨みして密告した、と疑われると思います。
何かいい方法はないでしょうか。
失業保険をもらっている間は社員とせず、アルバイトという形で使っているとのこと。その人と社長の間では、給料ではなくアルバイト代として手渡しで支払い、なおかつ領収書はその人の奥さんの名前で領収書を切っているということでした。
その場合明らかに不正受給ですが、証拠としては何も残っていないようですし、会社はその人とは関係ない、といってしまえばそれまででしょうか。 不正受給をしている人は丸々1年不正受給をしているようです。
私の友人はその会社で働いていましたが、売上数字が上がらないということで、給料を下げられた上、今後どうするのか、給料をさらに下げて、社員として働くか、それとも別の職を探すか、ということを問い詰められ、結局退職しました。
社員として働いていた人の給料を下げて、失業中の人を別人として扱って雇いアルバイト代を支払っている。
なんか腑に落ちなくてスッキリしません。 そのことは会社内でしかわからないことらしく、会社以外の人は誰も知らないということなので、もし私が密告したらその辞めた友人が、辞めさせられたことを逆恨みして密告した、と疑われると思います。
何かいい方法はないでしょうか。
不正受給なんてありえない!
本気で仕事したいのに、仕事がない人の為の失業保険なのに、許せない!
なんの為に雇用保険払っているのか・・・密告してください!
その人の為にも。
ちなみに、不正受給の場合、受給した金額の三倍返しなので、かなりの金額になります。
結果報告よろしくお願いします。
密告は職業安定所に、密告したらいいですよ。
みんなの為です。
本気で仕事したいのに、仕事がない人の為の失業保険なのに、許せない!
なんの為に雇用保険払っているのか・・・密告してください!
その人の為にも。
ちなみに、不正受給の場合、受給した金額の三倍返しなので、かなりの金額になります。
結果報告よろしくお願いします。
密告は職業安定所に、密告したらいいですよ。
みんなの為です。
失業保険の受給期間と受給金額の算出方法
これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?
10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。
どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?
10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。
どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 過去6か月の暦日数
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
関連する情報